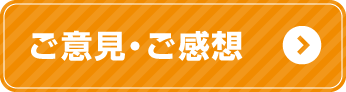介護最前線Front line of Nursing

十勝リハビリテーションセンター
先進リハビリテーション推進室
理学療法士
安部千秋(あべ せんしゅう)氏
回復期の高度なリハビリテーション医療を
肢体不自由児に対する“動くリハビリ”に応用
小児期から将来を意識した長期的な支援を行う
十勝リハビリテーションセンターは、最先端のリハビリテーション機器を数多く取りそろえるリハビリテーション専門病院である。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師をあわせて152名のセラピストがリハビリテーション医療に携わっている。先進リハビリテーション推進室には、ロボットや最新の電子機器が集められており、その様子はバックナンバー(リンク)で紹介した。
同センターでは、成人だけでなく肢体不自由児のリハビリテーションにも力を注いでいる。脳性麻痺や発達遅滞の子どもたちに対して包括的な支援を実施。学校など地域とも密に連携し、長期的に“動くリハビリ”を推進している。
先進リハビリテーション推進室の理学療法士・安部千秋氏に小児リハビリテーションの実践と支援の工夫についてお話を伺った。
同センターにおける小児リハビリテーションの実際
十勝リハビリテーションセンターでは、開院当初から脳神経疾患・運動器疾患・廃用症候群など成人のリハビリテーションとともに、肢体不自由児のリハビリテーションにも力を入れてきた。十勝エリアから150名程度が通院し、その多くが週1、2回の頻度でリハビリテーションを行っている。もっとも多いのが「精神・運動発達遅滞」という、発達過程において運動能力や精神能力に何らかの遅れが見られる子どもだ。脳に器質的な原因が見つからない子が4割を占めるほか、脳性麻痺、ダウン症候群などの染色体異常を持つ子もいる。

理学療法士16名、作業療法士10名、言語聴覚士3名が、回復期のリハビリテーションと並行して肢体不自由児に対するリハビリテーションにも従事している。障害が重度で通院が困難な子どもに対しては、本人と介助する家族が抱える問題にセラピストらが家庭を訪問して支援し、十勝エリアの全体のリハビリテーション医療を支えている。

 小児用の下肢装具
小児用の下肢装具
自分の体に対して、気づきを得ていく期間
回復期と小児のリハビリテーションはどのような点に違いがあるのだろうか。理学療法士の安部千秋氏は次のように話す。
「小児の運動療法は機能改善はもちろんですが、数年後の身体の機能を予測し、今ある運動機能を使って、日常生活をどのように過ごしていくかという視点が大事になります。運動機能の改善や歩行、姿勢の安定などは理学療法士が、食事などの日常生活動作や作業、学習に関することは作業療法士が支援し、言語の遅れや嚥下(食べることや飲み込み)に問題がある子には言語聴覚士がついて、その子の年齢や環境、状況に合わせて包括的なリハビリテーション医療を提供しています」。
学童期になると、子どもに課題が出てくる麻痺があって友達と同じ速さで歩けない子、リコーダーが吹けない子などの課題が出てくる。
「自分ができないことと向き合い、苦手なことを自覚する。そこからどうしたらみんなと同じ活動ができるか工夫しつつ、自尊心を高めることが精神面の成長につながります。 自分の体に対していろいろな気づきを得ていく期間として、小児リハビリテーションはとても重要です」。
就労を目指したリハビリテーション治療を目標に
運動機能以外にも知的障害や発達障害、さまざまな合併症が複雑にかかわることが多い肢体不自由児のリハビリテーションでは、最終的な目標をどのように設定するのだろうか。
安部氏は、「歩ける子、動ける子にかんしては、地域での就労を目指したリハビリテーション治療にとり組んでいます。子ども自身はもちろんまだ理解していないのですが、楽しく学校生活を送る延長線上に、将来働いて自分の力でお金を稼ぐことを意識しながらリハビリテーションプログラムを立案していくことも大事です」と答えた。事業所での就労や一般企業へ就職する人もいる。
かつて肢体不自由児の治療は、運動機能の改善が最優先とされてきた。しかし、近年は、歩行など粗大運動の獲得ばかりでなく、成人期以降の生活も見据え、小児期から生活機能・生活スキルを向上させていくことが重要と考えられている。
小児期から将来を考える例として挙げられるのはトイレの1人利用だ。
障害のある人が就労する際、職場での介助体制の確保がむずかしく、1人でトイレを利用できるかどうかが課題になることも多いという。ただし、小・中学生は、親や先生が手伝ってくれるため、1人でトイレを利用する重要性を理解できない子がほとんどだ。18歳になり就労や1人で外出できるようになりたいと意識したときに、初めてトイレの1人利用が、本人が成し遂げたい目標になる。脳性麻痺のある人の歩行をサポートするロボット(ゲイトトレーナー)などを導入し、トイレの訓練にも使われた事例を紹介してくれた。
学校とも連携し、“動くリハビリ”を支える
脳性麻痺児の場合、小学1〜2年生は重要な時期になる。学校が生活の中心になるタイミングで、どれだけ校内を歩いて移動できたかが将来の歩行能力に大きく影響するという。これは世界的な知見だ。2年生に進級した際、1年生の担任から「車椅子で移動していた」という申し送りがあると、歩く機会が大きく失われてしまう。将来を考えると、この状況は可能な限り避ける必要があるのだ。
歩くことがかなり困難な子には、その大変さを少しでも軽減できるような運動プログラムを実施する。長い距離を歩けない子は、学校内の移動でできるだけ車椅子を使わないことを目標に立てる。日常的には歩いていないという子も、立ち上がりや車椅子に移乗するという基本的な動作を定着させて自立を支援していく。
車椅子での移動が日常的になってしまうと虚弱になり、加齢の影響も受けやすくなるため、小児の時期から“動くリハビリ”を長期的に実践していくことが、将来のQOLを維持するために不可欠だといえる。
本人の歩行や体の状態を学校の関係者にも周知するため、リハビリの様子を見てもらったり、セラピストが学校に出向き、学習環境や姿勢保持装具を調整したりすることもある。家庭よりも学校の方が能力を発揮する子どももいるという。
「小児リハビリは病院内だけで完結するものではありません。地域との連携を密にしていく努力が必要になります」
【生活や学習活動をサポートする補装具】

前もたれの姿勢で立ち、脊柱の伸展を促す立位保持装置。全身の伸展運動が出やすく、上肢活動も引き出しやすい。

「バンビーナ」
姿勢や座位を保持し、食事や日常生活を楽にする。学校で使われることもある。

骨盤と体幹をしっかり支え、転倒を恐れず安心して動き回れる歩行器。
小児リハビリテーションを支える最新機器
小児専用のリハビリ支援ロボットはまだ十分に発展しておらず、成人向けの機器を応用して使用している段階だ。「先進リハビリテーション推進室」で活躍している最新機器を紹介してくれた。
【下肢・歩行リハビリ機器】

VR内の目標物にリーチ動作をくり返して行うリハビリテーション機器。目標物を見つける機能やリーチするための体幹機能の向上が期待できる。楽しみながら苦手な姿勢に慣れていくことも可能になる。前傾姿勢を不安がっていた子がこの機器を活用したリハビリテーションで靴のベルトの止め外しができるようになった。

細かい動作を3Dで分析できる。短時間で計測が可能で、結果を視覚的にわかりやすく、すばやく提示してくれるため、本人・家族・学校関係者とのカンファレンスにも役立つ。

麻痺や筋力低下がある子どもの歩行を効率的にサポートする。股関節の動きを左右のモーターに内蔵された角度センサーで検知。制御コンピューターがモーターを駆動させる。トイレ内での移乗獲得を目指した練習にも活用。
【手指のリハビリ機器】

手のひらを開き、指の曲げ伸ばしや手指を1本ずつ動かす練習をする。手指機能の改善と手の筋緊張やこわばりが和らぐ。
【歩くことを支援する電気刺激装置】

脳性麻痺児に生じる足の変形として踵が浮いてしまう尖足(せんそく)がある。
フランスベッドが提供する歩行神経筋電気刺激装置L300Go®は、「尖足(せんそく)」と、足首やつま先を持ち上げる筋力が低下し、足首が上がらなくなり、足先が垂れ下がる「下垂足」に対し、電気刺激を与え歩行をサポート。
歩くリズムを判定し、足首を上がりやすくさせられるため、歩行の非対称性を軽減する。
また、電気刺激を与えることで足の裏をつけてバランスをとる感覚を学習できる。未就学児から使用できるSサイズもあり、両足装着も可能だ。

L300Go®の装着とボツリヌス療法を併用した成功事例
安部氏は9歳の遺伝子疾患と精神運動発達遅滞を有する症例を紹介してくれた。
両手をつかんで介助しないと歩けず、成長に伴い母親の負担も大きくなっていた。興奮するとのけぞって歩行介助が大変、バスステップに登るのが大変で通学バスに乗れないといった複合的な問題も抱えていて、それぞれ専門のセラピストが支援し、1つずつクリアしていった。
そのような中でセラピストたちは、その子が歩行できる潜在能力を適正な評価によって見定め、ボツリヌス治療における理学療法にハーネスを用いた安全に歩行できる環境調整とフランスベッドのL300Go®を使用し、積極的な歩行練習を実施した。
「さまざまな治療とリハビリテーションツールを組み合わせ、1〜2年格闘した結果、10歩、歩くことができました。手を振り回して歩く姿を見て、親御さんは、我が子にそこまで歩く能力があったのか涙していました。私たちセラピストにとっても足の裏をつけて歩く、動くリハビリが非常に重要だという気づきを得た成功事例です」と安部氏は目を輝かせる。
現在は、18歳になったときに介助を必要としながらも「歩くこと」を目標にリハビリに励んでいると教えてくれた。
連絡先
十勝リハビリテーションセンター
〒080-0833 北海道帯広市稲田町基線2-1
TEL 0155-47-5700
https://www.hokuto7.or.jp/hospital/rehacenter/top/