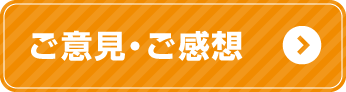研究・事業助成採用事例Examples of research and business grants
市民団体ゆめカステラプロジェクト 代表
三串 伸哉氏
令和6年度(第35回)/事業助成『第5回長崎嚥下食デザートコンテスト』
好きなものを食べてもらうことで
摂食嚥下障害の認知と理解を促したい
食べることや飲み込むことができなくなり、食事や水分がうまくとれない状況──これを「摂食嚥下障害」という。在宅療養中の高齢者に多く、毎年約2万人が新たに発症するといわれる。ゆめカステラプロジェクトは、この摂食嚥下障害の認知向上を目的とした啓発活動を行う市民団体で、医師、病院や施設の管理栄養士、介護事業者などで構成される。地域住民に向けたセミナーや勉強会の開催が活動の中心だが、年に一度『嚥下食デザートコンテスト』を開催し嚥下食の開発を喚起する。昨年11月に実施した第5回が財団事業助成の対象となった。
誤嚥性肺炎で亡くなる人が多い理由
第5回「長崎嚥下食デザートコンテスト」が、昨年11月、長崎県、長崎市、活水女子大学、長崎県栄養士会の後援を得て開催された。主催は、「好きなものを食べて生きていく」を理念に、摂食嚥下障害の認知活動を行う「ゆめカステラプロジェクト」。2017年1月に医療、介護従事者の勉強会の中で発足した市民団体だ。日ごろは地域住民に向けたセミナーや勉強会などを開催しているが、年に一度、嚥下食デザートコンテストを開催している。2020年に第1回をスタート。おいしく食べやすい嚥下食の開発活動を通じて摂食嚥下障害の啓発活動を展開する同団体を象徴するイベントとなった。
事業助成に応募したのは、ゆめカステラプロジェクト代表の三串伸哉さん(47)。三串さんは歯科医師、嚥下に関する専門家である。歯科医療の中でも摂食嚥下障害の認知向上に取り組むようになったいきさつをこう語った。「訪問診療で飲み込みの悪い人としてリハビリや評価を行っていると、毎年多くの人が誤嚥性肺炎で亡くなっている現実を直視します。誤嚥性肺炎自体は細菌感染症なので、病院に入院すれば抗生剤で治療できます。問題は退院後です。自宅や施設に戻ってから誤嚥が続いたり、抵抗力の低下や口腔内の環境が不良だと再び誤嚥性肺炎を起こす。そのたびに体力は失われていく。とろみ付けや口腔衛生管理、栄養管理などで予防ができる感染症なのにもかかわらず、その数が減らないのが現状なのです」



ムース食・ミキサー食ばかりで満足できるか
食べることや飲み込むことができなくなり、食事や水分がうまくとれない状態を摂食嚥下障害という。脳血管疾患による麻痺、神経・筋疾患、加齢による筋力低下などが原因で、毎年約2万人の高齢者が新たに発症するという。三串さんは続ける。「生活の場(地域)で起きている誤嚥を是正しない限り、誤嚥性肺炎は繰り返し感染し発症します。普段の生活から本人や周りの人々が摂食嚥下障害を理解し、予防、対策できるようになれば肺炎も窒息も減るでしょう。その一方で、矛盾するようですが、摂食嚥下障害があってもリスクを承知で好きな物を食べる、選ぶ権利があってもいいと私は思います。障害により自分の好きなものを食べられないことでQOL は低下しますから。嚥下食デザートコンテストの狙いもそこにあります」
コンテスト開催の動機には、医療・介護事業者が提供する摂食嚥下障害の食事メニューへの物足りなさもあるようだ。誤嚥の予防に軸足を置くのは当然とはいえ、ムース食やミキサー食など安全に配慮した食事の提供を指導するばかりでは、患者さんは食べたいものを食べられない。街中にある美味しい食べ物を食べられるように、食材の選択肢や調理・加工のアイデアを広げることで嚥下食のすそ野を広げられたらという思いがあるという。
コンテストの話に戻ろう。第5回のテーマは「長崎県産品」。県内の医療、福祉施設、福祉科や調理科のある学校などに開催を告知したところ、20作品のレシピ応募があった。その中から学生部門、一般部門ともに5作品・5チームが決勝審査に進んだ。結果、学生部門グランプリ及びセレクト賞(参加者が選んだ優秀作品)は長崎県立長崎南高等学校の「びわきんとん」、一般部門のグランプリは特別養護老人ホームこえばるの「トマトようかん」、セレクト賞は要介護者家族の患者の「なめらかすてらチョコバナナ」がそれぞれ受賞。コンテストに集まった作品はレシピ集として印刷、冊子にして、摂食嚥下障害をもつ家族や医療・介護関係者に配布された。


嚥下食へのお店の理解も高めていきたい
「今回の特徴として、学生部門では医療・福祉にかかわる学生のほか、家庭部に所属する普通科の学生にもアプローチできました。また西日本新聞の取材があり記事が掲載されたことで、我々の活動を知ってくれる方が増えたと思います。コンテストを通じて、参加者は摂食嚥下障害や嚥下食に対する理解を深めてくれたと思います」。コンテストの目的には、美味しく食べやすい嚥下食の開発もある。優秀な作品が生まれれば製品化しない手はない。事実、コンテストから生まれた製品もある。第1回のグランプリに輝いた『Uni Cake(ユニケーキ/スポンジ生地をとろけるほど柔らかくし、フルーツも一度すりつぶしなめらかな食感に仕上げている)』がそれ。地元の老舗洋菓子店に頼んで作ってもらい、今年6月から店頭販売を開始した。ちなみに同団体の開発第一号は、団体名にもなったカステラの嚥下食(商品名『なめらかすてら』)だった。
コンテスト開催にあたり、三串さんが毎回苦労しているのは募集告知の難しさという。毎年、福祉科や栄養科のある学校や高齢者施設、病院などに募集要項を郵送しているが、反応はかんばしくない。今後はより広く、多くの人にコンテストへの関心を高めてもらうには、地域の掲示板やSNSでの告知がより重要と考えている。そしてもう一つの課題は開催費用の確保。「助成を受けられないと開催自体が難しくなります。毎回、どこかの助成制度を利用させてもらっています。フランスベッドさんのご支援は今回が初めていただき、ありがとうございました。今後は、摂食嚥下障害への理解を促進していくと同時に、飲み込みの悪い人でも食事を楽しめるお店が増えるような活動にも力を注いでいけたらと思います」と三串さん。
たしかに、摂食嚥下障害の人にとっての外食環境は寂しい限りだ。大型店でも車椅子でテーブルに着くのが精いっぱいといったところ。ゆめカステラプロジェクトの次の一手に期待したい。
連絡先
ゆめカステラプロジェクト
代表 三串伸哉
Mail:yumekasutera@gmail.com